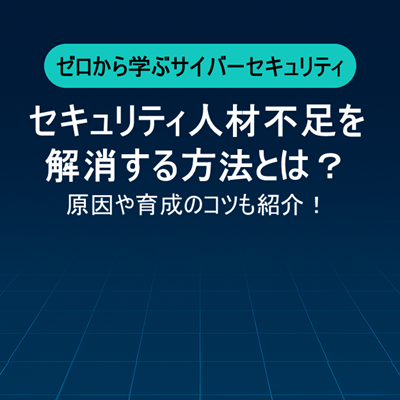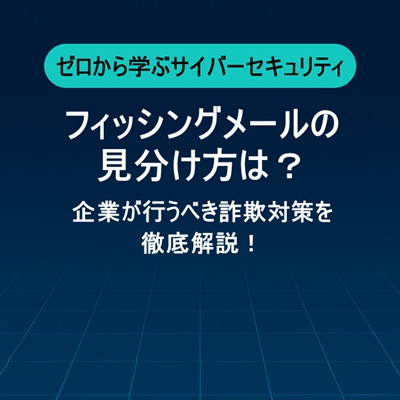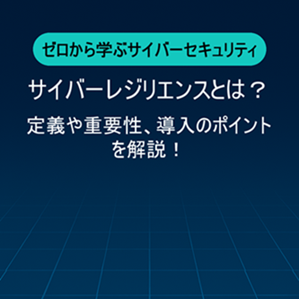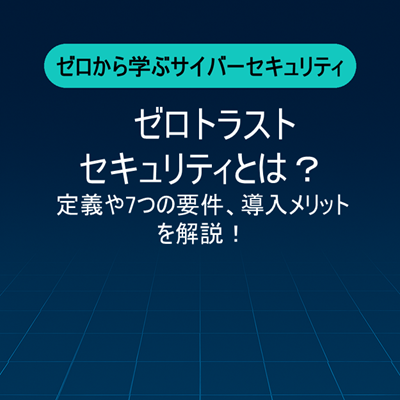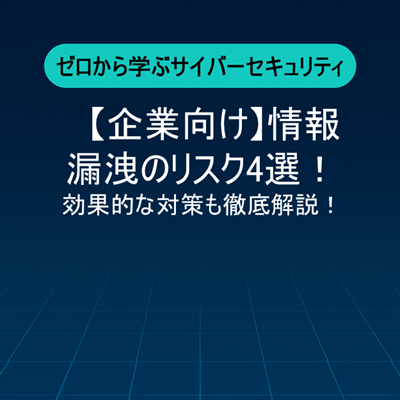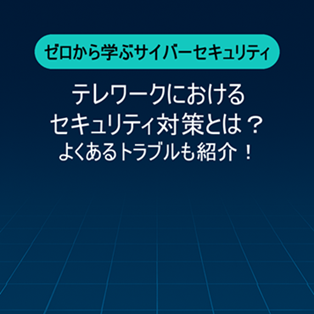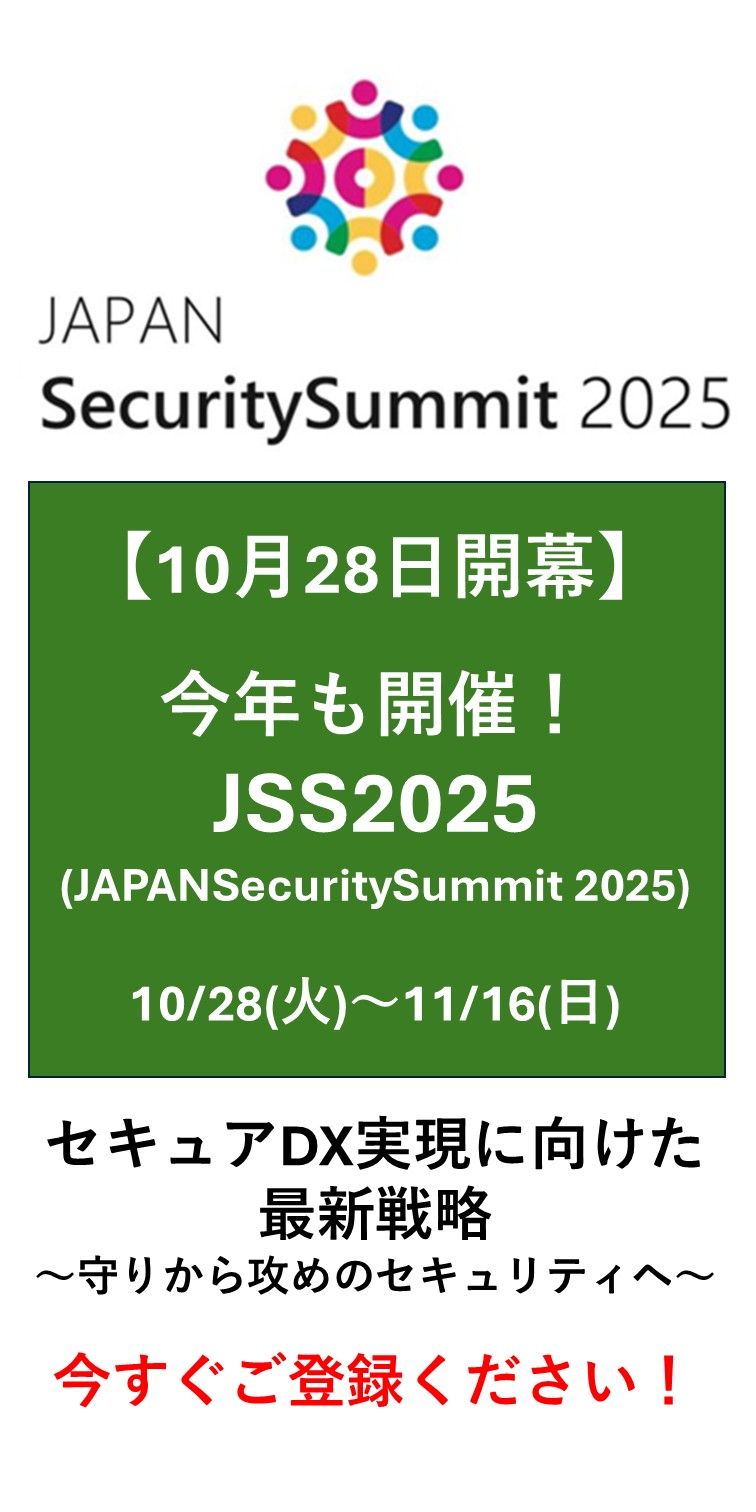サイバー攻撃とは?目的や種類、被害例や対策法を徹底解説!
近年、サイバー攻撃による被害が企業や団体、さらには個人にも広がっており、対岸の火事とはいえない状況に陥っています。
情報漏洩や業務停止、金銭的損失など、サイバー攻撃の影響は深刻であり、対策の遅れは企業の存続すら脅かしかねません。
そんなサイバー攻撃から身を守るためには、正しい知識を身につけておくことが大切です。
そこで今回は、サイバー攻撃の定義やその目的、種類や被害事例を紹介します。
効果的な対策についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
サイバー攻撃とは?
では早速、サイバー攻撃の定義や歴史、目的について詳しく見ていきましょう。
サイバー攻撃の定義
サイバー攻撃とは、個人や企業、組織の情報システムに不正アクセスして、データを盗んだり、破壊したり、業務を妨害したりする行為のことです。
攻撃者は、ハッカーやクラッカー、国家的な組織など多岐にわたり、その目的もさまざまです。
これまでは、金銭目的や愉快犯的な要素が主となっていましたが、現在では企業スパイやテロ行為、政治的メッセージの発信など、組織的な背景を持つ攻撃も増えています。
サイバー攻撃の歴史
サイバー攻撃は、インターネットが普及し始めた1980年代ごろに始まりました。
初期はウイルスの作成やネットワークへの侵入など、技術者によるいたずらや能力誇示が主な動悸でしたが、2000年代以降は企業や政府機関を標的とした高度で巧妙な攻撃が増加しました。
以降、ランサムウェアやサプライチェーン攻撃など、攻撃手法も目的も複雑化の一途をたどっています。
サイバー攻撃の目的
サイバー攻撃の目的は、大きく分けると以下4つです。
・金銭的利益
・情報の窃取
・業務妨害
・政治的・社会的主張
例えば、ランサムウェアによる身代金要求は金銭目的、フィッシング攻撃はIDやパスワードの窃取目的であることが多いです。
国家間では、重要インフラの麻痺や機密情報の収集を狙った攻撃もあり、地政学的リスクの一環としても注目されています。
サイバー攻撃の代表的な種類6選!
サイバー攻撃にはさまざまなものがありますが、中でも代表的なのは以下6つです。
・DDoS攻撃
・マルウェア攻撃
・ランサムウェア攻撃
・フィッシング攻撃
・サプライチェーン攻撃
・ビジネスメール攻撃
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
DDoS攻撃
DDoS攻撃は、大量の通信データを一斉に送り付けて、Webサイトやサーバーをダウンさせる手口です。
複数の端末から攻撃を仕掛けることで、通常のアクセスを妨害し、サービスの提供を停止させます。
オンラインショップや予約システムなど、常時稼働が求められるサイトでは致命的な損害に繋がる恐れがあります。
近年では、金銭目的や政治的メッセージを伴う攻撃も増加傾向にあるため、事前に対策しておかなければなりません。
マルウェア攻撃
マルウェアとは、悪意のあるソフトウェアの総称です。
有名なものとしては「トロイの木馬」などが挙げられます。
これらのソフトウェアは、ユーザーが気付かないうちに端末に感染し、データを盗み出したり、破壊したりします。
感染経路はメール添付ファイルやWebサイト、USBメモリなど多岐にわたるため、細心の注意が必要です。
マルウェアの一部は、他の攻撃の踏み台として使われることもあり、企業の機密情報や顧客データが狙われるリスクも高まっています。
ランサムウェア攻撃
ランサムウェアは、システムやデータを暗号化し、復旧のために金銭(多くの場合は仮想通貨)を要求するマルウェアの一種です。
感染経路はメールやサイトなど多岐にわたります。
ランサムウェアの復旧手段は限られているため、金銭を支払ってしまう企業も多いですが、完全な復旧が保証されるわけではありません。
場合によっては、業務停止や信用失墜などに直結するケースもあるため、徹底的に対策をしておく必要があります。
フィッシング攻撃
フィッシング攻撃とは、別名フィッシング詐欺とも呼ばれています。
これは、偽のメールやWebサイトを使ってユーザーを誘導し、ログイン情報やクレジットカード番号などを盗む攻撃です。
フィッシング詐欺は、企業や団体だけでなく、個人がターゲットになるケースもあるため、事前に正しい知識を身につけておかなければなりません。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、標的企業ではなく、その取引先や外部委託先などを経由して侵入するサイバー攻撃です。
セキュリティが甘い中小企業を踏み台にし、最終的に大企業のネットワークにアクセスするのが特徴です。
攻撃者は信頼関係を悪用するため発見が遅れがちで、甚大な被害に繋がるケースもあります。
ビジネスメール攻撃
ビジネスメール攻撃は、社内の関係者や取引先を装った偽メールを使い、従業員に不正送金や機密情報の提供を促す攻撃です。
攻撃者は、メールアカウントを乗っ取るか、巧妙に似せたアドレスで信頼を獲得しようとします。
金銭的な被害は、1件当たり数千万円にのぼることもあり、特に経理や管理部門が狙われやすいです。
サイバー攻撃による被害例
サイバー攻撃を受けてしまった場合、以下のような被害を被る可能性があります。
・情報漏洩
・金銭的被害
・社会的信用の低下
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
情報漏洩
サイバー攻撃の中でも特に深刻なのが「情報漏洩」です。
企業が保有する顧客データや取引先情報、従業員の個人情報や研究データなどが外部に流出すると、甚大な被害に繋がります。
漏洩した情報が悪用されれば、顧客からの信頼を失うだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
また、個人情報保護法などに違反すれば、行政処分や罰金の対象にもなるため、常に警戒しておかなければなりません。
金銭的被害
サイバー攻撃は、直接的な金銭被害をもたらします。
よくあるのが、ランサムウェアによってデータが暗号化され、身代金を要求されるケースです。
また、偽の送金指示メールに従って、多額の資金が流出する「ビジネスメール詐欺」なども増加傾向にあります。
さらに、攻撃の影響で業務が停止した場合、生産や販売機会の損失、システム復旧や調査費用の発生など、経営に大きなダメージを与えます。
中小企業によっては、こうした費用が致命傷になることもあるため、事前の備えが重要です。
社会的信用の低下
サイバー攻撃による被害が公になると、企業の「信用力」に大きな影響を及ぼします。
顧客や取引先からは「セキュリティ管理が甘い企業」とみなされ、新たな取引や契約の機会を失う可能性があります。
また、株価の下落やメディア報道による風評被害も深刻です。
特に上場企業や公共性の高い業種では、社会的信用の低下が企業存続に直結することもあります。
一度失った信用を取り戻すには、長い時間とコストがかかるため、信頼を守る意味でもセキュリティ対策はしっかりと行っておかなければなりません。
サイバー攻撃を防ぐためにできること
サイバー攻撃を防ぐためには、以下のような対策を行うことが大切です。
・情報セキュリティ教育の徹底
・セキュリティソフトの導入
・二段階認証の活用
・サイバー保険の活用
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
情報セキュリティ教育の徹底
多くのサイバー攻撃は、人の不注意や知識不足を突いて行われます。
実際に、偽のメールに添付されたファイルを開いたり、不審なリンクをクリックしたりといった行動がきっかけとなるケースは後を絶ちません。
そのため、従業員一人ひとりが脅威を正しく理解し、日常的に注意を払えるようになることが大切です。
フィッシングメールの見分け方や、安全なパスワードの作成など、基本的なセキュリティ知識を教育することで、組織全体の防御力が高まります。
セキュリティソフトの導入
企業のIT環境を守るためには、信頼性の高いセキュリティソフトの導入が欠かせません。
セキュリティソフトを導入することで、ウイルスやマルウェア、不正アクセスなどを検知しやすくなるため、被害を未然に防げるようになります。
ただし、セキュリティソフトにはさまざまな種類があり、それぞれで特徴が大きく異なるため、目的や予算に合ったツールを慎重に探していきましょう。
二段階認証の活用
IDとパスワードだけでは、サイバー攻撃を完全に防ぐことができません。
特にパスワードが漏洩した場合、不正ログインを許してしまう恐れがあります。
そこで有効なのが「二段階認証」です。
ログイン時にパスワードに加えて、スマートフォンへのワンタイムコードや指紋認証など、もう一段階の認証を行うことで、不正アクセスのリスクを大幅に軽減できます。
中でも、クラウドサービスや社内システムなど、重要な情報にアクセスする際は二段階認証が役立ちますので、ぜひ取り入れてみてください。
サイバー保険の活用
どれだけ対策をしても、サイバー攻撃のリスクを完全にゼロにすることはできません。
そこで注目されているのが、サイバー保険です。
サイバー保険は、情報漏洩時の金銭的損害やシステム復旧費用、広報対応費用などをカバーしてくれるため、被害発生時の経済的負担を軽減しやすくなります。
こちらもさまざまな種類がありますので、費用対効果や補償内容などを吟味しつつ、自社に合った保険を慎重に探していきましょう。
まとめ
サイバー攻撃は、年々高度化・巧妙化しています。
サイバー攻撃を受けると、情報漏洩や金銭的損失、信頼失墜といった深刻な被害が生じるため、日ごろからしっかりと対策をしておかなければなりません。
中には「うちは大丈夫」と油断してしまうケースもありますが、被害に遭ってからでは遅いため、今できる対策を一つひとつ確実に実行していきましょう。