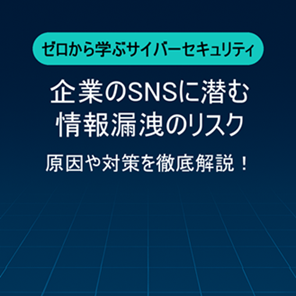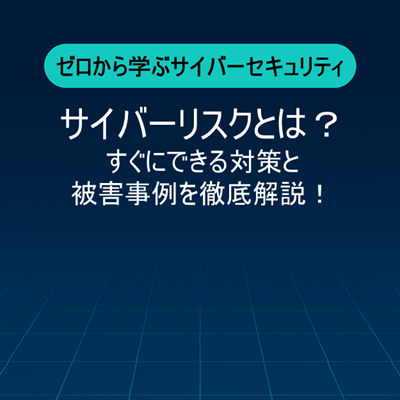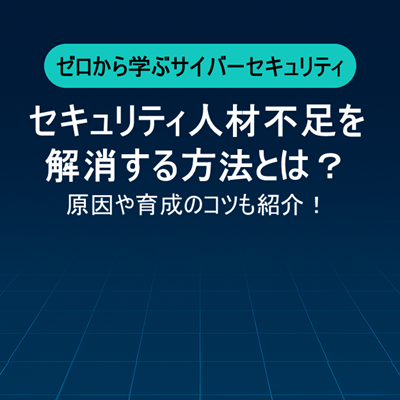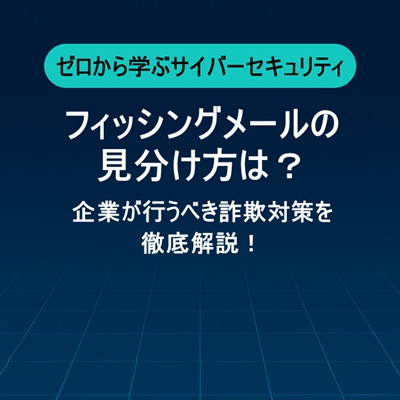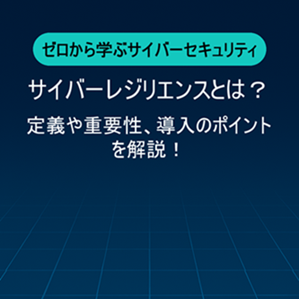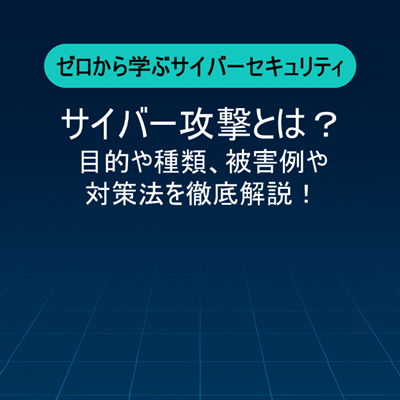ゼロトラストセキュリティとは?定義や7つの要件、導入メリットを解説!
情報通信技術の進化に伴い、近年ではサイバー攻撃の手口が巧妙化しています。
最近では、リモートワークやクラウドツールの普及によって、社内外からシステムにアクセスする機会が増えており、企業には「これまで以上のセキュリティ対策」が求められています。
そこで注目されているのが、ゼロトラストセキュリティです。
今回は、そんなゼロトラストセキュリティの定義や7つの要件、導入メリットについて詳しく解説していきます。
ゼロトラストセキュリティとは?
ゼロトラストセキュリティとは、社内外のネットワークやデバイスのすべてに脅威が潜んでいることを前提としたセキュリティモデルです。
「何も信頼しない」
「全てのアクセスを常に検証する」
この考え方は、従来の「社内は安全、社外は危険」という常識を覆すものであり、現代に合ったセキュリティ対策として注目を集めています。
これまでの境界防御では、VPN経由での侵入や内部不正に対応できなかったのですが、ゼロトラストセキュリティの場合は、
・ユーザー認証
・デバイス認証
・最小権限アクセス
・リアルタイム監視
といったさまざまな対策を組み合わせるため、あらゆる側面からセキュリティ性を維持・向上させられるのです。
ゼロトラストセキュリティが求められている背景
ゼロトラストセキュリティが求められている理由には、以下のような背景があります。
・クラウドサービスが普及している
・リモートワークが増加している
・サイバー攻撃の手口が巧妙化している
・ゼロデイ攻撃が増加している
便利なクラウドサービスが続々登場している昨今においては、これまでの「社内は安全」という概念が通用しなくなりました。
また、リモートワークの増加に伴い、社内外からのアクセスが増えており、従来のセキュリテでは十分な防御が難しくなっています。
さらに、現代ではサイバー攻撃の手口が巧妙化しており、新たに発見された脆弱性を突く「ゼロデイ攻撃」も増加中です。
このような理由から、ゼロトラストセキュリティへの注目が高まっているのです。
ゼロトラストセキュリティを導入するメリット
ゼロトラストセキュリティは、業種や業界、規模を問わずさまざまな企業に注目されています。
では、企業がゼロトラストセキュリティを導入することで、一体どのようなメリットを得られるのでしょうか。
セキュリティリスクが低減する
ゼロトラストセキュリティは、誰も信頼しないことを前提に全てのアクセスを検証・防御するため、内部不正や不正侵入のリスクを大幅に軽減できます。
従来型の境界防御ではカバーしきれなかった、リモートワークやクラウド環境などにも対応可能です。
また、攻撃を受けた際の影響範囲も限定されやすく、被害拡大を防ぐ構造になっていることも大きな特徴です。
情報漏洩を防げる
ゼロトラストセキュリティでは、ユーザーやデバイスの認証を徹底的に行い、アクセス権限を最小限に制限します。
これにより、万が一不正アクセスが発覚した場合でも、機密データへの到達を防ぎやすくなるのです。
さらに、全ての通信やデータ操作ログを記録・監視することで、不審な挙動をいち早く検知・遮断できるため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。
安全なリモートワーク環境を構築できる
近年注目を集めているリモートワーク。
比較的新しい働き方ではあるものの、オフィスの縮小や業務効率の向上など、さまざまな効果に期待できます。
そんなリモートワークでは、システムを活用して社内外の人間とコンタクトを取ることが多いです。
ゼロトラストセキュリティを導入することで、場所に関係なく安全なアクセスを実現できます。
特定の端末やユーザーの状態を常にチェックし、問題がある場合は自動でアクセス制限をかける仕組みも整えられているため、どこにいても安心して業務を遂行できるようになるのです。
コンプライアンス強化に繋がる
情報セキュリティの強化は、コンプライアンスの観点でも重要です。
ゼロトラストセキュリティを導入することで、個人情報保護法やISMSなどの基準に準拠した管理体制を整えていると判断されやすく、取引先や顧客からの信頼獲得にも繋がります。
また、情報漏洩や不正アクセスの予防策を明確に示すことで、企業としてのリスク管理意識の高さをアピールできるため、イメージの向上にも期待できるでしょう。
ゼロトラストセキュリティに必要な7つの要件
ゼロトラストセキュリティを実現するためには、以下7つの要素を総合的に整備する必要があります。
・デバイスセキュリティ
・ネットワークセキュリティ
・アイデンティティセキュリティ
・ワークロードセキュリティ
・データセキュリティ
・可視化と分析
・セキュリティの自動化
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
デバイスセキュリティ
ゼロトラストセキュリティにおいては、社内外を問わず接続される全てのデバイスを把握し、信頼できる端末のみを業務システムにアクセスできるようにすることが大切です。
ウイルス対策ソフトの有無や状況、OSやソフトウェアの更新状況、端末の暗号化などを確認することで、強固なセキュリティ体制を維持できます。
ネットワークセキュリティ
ゼロトラストセキュリティでは、従来の「社内は安全」という常識を捨て、社内外問わず全ての通信を検証・暗号化する仕組みが求められます。
具体的には、マイクロセグメンテーションによってネットワークを細かく分割し、必要最小限のアクセス権限に基づいて通信を制御することが大切です。
アイデンティティセキュリティ
システムをサイバー攻撃などの脅威から守るためには、適切なユーザー認証が欠かせません。
多要素認証やシングルサインオン、IDaaS(ID管理サービス)などを利用し、なりすましや不正アクセスを防ぎましょう。
また、役職や業務内容に応じて、きめ細かなアクセス制限を行う「最小権限の原則」を徹底することも重要です。
ワークロードセキュリティ
ワークロードとは、クラウド上で動作するアプリやサービスのことであり、これらのセキュリティもゼロトラストセキュリティの対象となります。
アプリやサービスごとに通信の可視化と制御を行い、不審な挙動を自動的にブロックする仕組みが求められます。
ただし、従業員が個人的にクラウドサービスを契約している場合、状況の把握が難しくなりますので注意してください。
データセキュリティ
「どこに、どんなデータがあるか」を把握し、それぞれに適切な保護を施すのがデータセキュリティです。
ファイル単位での暗号化やアクセスログの記録、データ分類やタグ付けなどを通じて、情報漏洩のリスクを最小化しましょう。
また、データセキュリティを強化するためには、ツールやサービスを活用するだけでなく、社内教育も重要ですので、定期的に研修を行うことをおすすめします。
可視化と分析
ゼロトラストセキュリティを導入するためには、システム全体の「見える化」を行うことが大切です。
ユーザーのログイン履歴やアクセス先、デバイスの動作状況などをリアルタイムで収集・分析し、異常を即座に検知・対応できるようにしておきましょう。
現在では、サイバー攻撃の手口が多様化していることもあり、専門知識を持つ外部企業に可視化と分析を委託するケースも増えています。
セキュリティの自動化
ゼロトラストセキュリティの効果を高め、効率よく監視や運用を行うためには、セキュリティの自動化が欠かせません。
近年では、アラート分析やインシデント対応などを効率化してくれるツールなども増えていますので、気になる方はぜひ検討してみてください。
ゼロトラストセキュリティ導入における課題と対策
世界中で注目されているゼロトラストセキュリティですが、以下のような課題もあります。
・コストと運用負担が増加しやすい
・ユーザーの利便性が低下することもある
コスト面や運用面の課題を解消するためには、段階的な導入や、クラウドサービスの活用がおすすめです。
また、ユーザーの利便性低下を防ぐには、シングルサインオンの導入など、利便性とセキュリティのバランスを取る仕組みを採用するのが効果的です。
まとめ
ゼロトラストセキュリティは、従来の「境界防御型」の考え方から脱却し、全てのアクセスを信頼しない前提でセキュリティを構築する新しいアプローチです。
一見すると、かなり斬新な取り組みに思えるかもしれませんが、サイバー攻撃の高度化やリモートワーク・クラウドの普及など、変化するIT環境に対応するには不可欠な考え方といえるでしょう。
導入にはコストや運用面での課題もありますが、段階的な実装や外部サービスの活用によって、リスクを抑えながら効果的に進められます。
情報漏洩やコンプライアンス強化、リモートワークの安全性向上といった多くのメリットを持つゼロトラストセキュリティは、企業規模を問わず検討すべき現代的なセキュリティ戦略です。
今よりもさらに強固なセキュリティ基盤を構築したいと考えている方は、ぜひ導入してみてください。