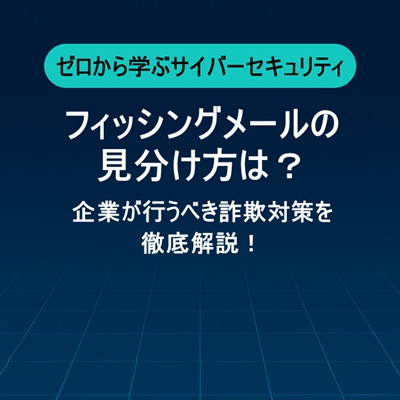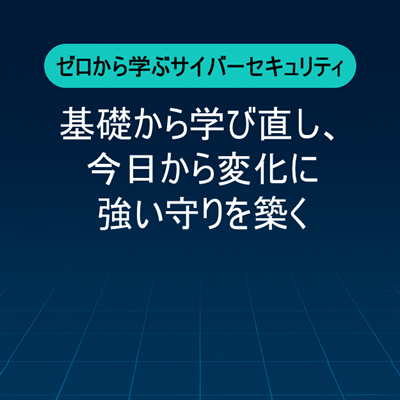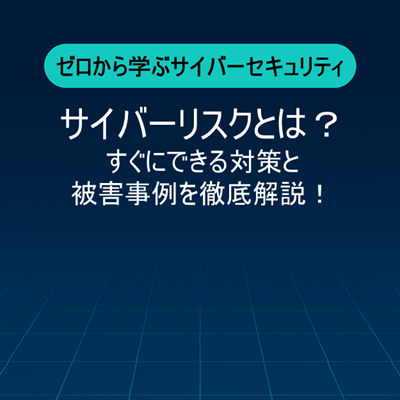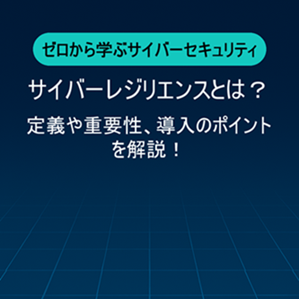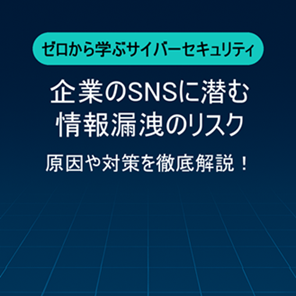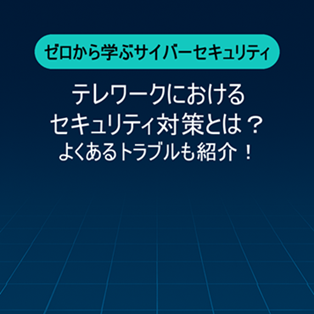【企業向け】情報漏洩のリスク4選!効果的な対策も徹底解説!
近年、企業を取り巻く情報漏洩リスクは深刻さを増しており、一度のインシデントが経営に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。
特にデジタル化が進む中で、社内外に蓄積された個人情報や顧客データ、機密資料などが不正アクセスや人為的ミスによって流出する事例が後を絶たず、対策の不備が致命的な被害を招くこともあります。
今回は、企業が抱える代表的な情報漏洩リスクと、それに伴うダメージ、さらに効果的な対策方法までを網羅的に解説します。
情報漏洩とは?
情報漏洩とは、企業や組織が保有している個人情報や機密情報、業務データなどが第三者に流出・拡散してしまうことです。
漏洩の原因には、不正アクセスやウイルス感染などの外的要因だけでなく、従業員の操作ミスや内部不正といった人的要因も含まれます。
特に現代では、情報をデータとして管理することが増えており、ちょっとしたミスや対策不足で重要なデータが漏洩してしまうことがあるため、しっかりと対策をしておかなければなりません。
情報漏洩に伴う企業のリスク
情報漏洩が発生した場合のリスクとして考えられることは、主に以下4つです。
・社会的信用が低下する
・刑事罰の対象になる可能性が高まる
・二次被害に繋がりやすくなる
・従業員の不安や不信感が強まる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
社会的信用が低下する
情報漏洩が発覚すると、企業のブランドや信頼性は一気に失墜します。
顧客や取引先は「この会社に情報を預けても大丈夫なのか?」という不信感を抱くようになり、契約の打ち切りや新規取引の減少に繋がるケースもあります。
特に個人情報の漏洩は消費者感情に直結し、SNSやメディアで拡散されることで、企業イメージが長期にわたり傷つく可能性があるため注意が必要です。
再発防止策を講じたとしても、一度失われた情報を取り戻すには長い時間と莫大なコストがかかります。
経営にとって「信用」が最大の資産であることを考えると、情報管理の失敗は致命的な経営リスクになるといえるでしょう。
刑事罰の対象になる可能性が高まる
漏洩した情報が法的に保護される個人情報や機密情報であった場合、企業は個人情報保護法や不正競争防止法などによって罰せられる可能性があります。
その他、損害賠償請求をされたり、刑事罰の対象になったりすることもあるため注意が必要です。
情報漏洩は単なるミスではなく、想像以上に大きなトラブルに発展してしまうこともあるため、徹底的に対策をしておかなければなりません。
二次被害に繋がりやすくなる
情報漏洩が起こると、二次被害が発生しやすくなります。
例えば、個人情報が流出したことが原因で、詐欺メールが送られたり、なりすましの被害に遭ったりとさまざまなことが考えられます。
そうなれば、大切な顧客や取引先の生活を脅かしたり、信用を失墜させたりといった事態にも繋がりかねません。
このように、情報漏洩の被害は、自社だけでなくその情報に関連する個人や組織にも広がってしまうのです。
従業員の不安や不信感が強まる
情報漏洩が発生すると、外部だけでなく社内にも深刻な影響を及ぼします。
特に、情報漏洩の原因が内部不正や管理体制の不備であった場合、従業員は「この会社で働き続けて大丈夫なのか?」と不安を抱くようになります。
そうなれば、離職率の低下や定着率の低下にも繋がり、業績不振や慢性的な人手不足に陥ってしまうこともあるため注意が必要です。
企業の情報漏洩は何が原因?
企業の情報が漏洩する原因として考えられることは、主に以下7つです。
・メールやFAXの誤送信
・デバイスの紛失・置き忘れ
・内部不正
・マルウェア感染
・設定ミス
・アカウントの管理不備
・システム障害
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
メールやFAXの誤送信
情報漏洩の原因として意外と多いのが、メールやFAXの「宛先間違い」です。
特に社外とのやり取りが多い部署では、複数の宛先に一括で送信するケースも多く、誤送信のリスクが高まります。
中でも、宛先の「To」「Cc」「Bcc」の使い方を誤ったことで、関係のない第三者に顧客情報や契約書などの機密情報が届いてしまう例が後を絶ちません。
メールやFAXは、一度送信すると取消ができないため、重要な情報を守るためにも、送信前にもう一度宛先をチェックしましょう。
デバイスの紛失・置き忘れ
ノートパソコンやUSB、スマートフォンなどのデバイスを外出先で紛失したり、置き忘れたりしたことが原因で、重要な情報が流出してしまうケースもあります。
特に、リモートワークや外出先での業務が増えた現代では、持ち運び可能なデバイスに重要情報が保存されていることも多く、万が一落とした場合のリスクは甚大です。
たとえパスワードをかけていたとしても、巧妙な手口で解除される可能性があるため注意してください。
内部不正
内部不正が原因で、企業の重要な情報が漏れ出してしまうケースもあります。
よくあるのが、退職予定者が顧客リストを持ち出して、競合他社へ転職したり、不満を持った従業員が報復として社外に機密情報を流出させるといった事例です。
中でも、意図的な情報漏洩は対策が非常に難しく、場合によっては想像以上に大きなトラブルに発展してしまうこともあるため、企業としてしっかりと対策をしていかなければなりません。
マルウェア感染
マルウェアとは、コンピューターなどに被害を与えることを目的とした悪意のあるウイルスです。
一度マルウェアに感染すると、情報漏洩をはじめとするさまざまなトラブルに繋がります。
身代金要求やデータ破壊など、いくつかのトラブルが一気に押し寄せてくることもあるため、セキュリティ対策を徹底的に行う必要があります。
また、マルウェアはメールに添付されたリンクやファイルなどから感染することもあるため、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高める工夫も必要です。
設定ミス
意図せぬ情報漏洩は、システムやクラウドツールの「設定ミス」からも起こります。
よくあるのは、社内限定で閲覧すべきファイルが「全体公開」設定になっていたり、アクセス制限が不十分な状態でクラウド上にアップされていたりといったケースです。
このような場合、意図せず第三者に見られてしまう可能性があり、それが原因で情報漏洩に繋がってしまうこともあります。
アカウントの管理不備
IDやパスワード管理がずさんなままでは、なりすましや不正ログインによる情報漏洩が起こりやすくなります。
中でも、パスワードを使い回していたり、退職者のアカウントを放置していたりといったケースは特に危険です。
また、パスワードが短く単純であれば、総当たり攻撃(ブルートフォース)で簡単に突破されてしまいます。
このような事態を避けるためには、多要素認証を導入したり、アカウント使用状況を徹底的に管理したりといった対策が必要です。
システム障害
システム障害によってバックアップデータが消失したり、本来閲覧できない情報が一時的に公開されてしまったりといった、技術的なトラブルによる情報漏洩も存在します。
特にサーバー移行時や、大規模なシステムアップデートの際には、想定外のエラーやデータ不整合が発生する場合があるため注意が必要です。
また、老朽化したインフラを使い続けていると、物理的な故障から機密情報が洩れるケースもあります。
このようなリスクを抑えるためには、定期的にシステム保守やリスク評価などを行い、障害発生時の即時復旧体制を整えておくことが大切です。
情報漏洩を防ぐために企業がやるべきこと
情報漏洩は、偶発的なミスから巧妙な攻撃まで、さまざまなことが原因となって発生します。
そのため、単一の対策では防ぎきれず、複数の視点からセキュリティ対策を実施することが大切です。
ここからは、情報漏洩を防ぐために企業がやるべきことをいくつか紹介していきます。
情報の取り扱いルールを決める
情報漏洩を防ぐためには、社内で情報の取り扱いルールを決めておくことが大切です。
例えば、
・どのような情報が機密に該当するのか
・どの手段で送信・共有すべきか
・ファイルはどこに保管しておくべきか
といった運用ルールを決めておくことで、人為的ミスを防ぎやすくなります。
このときのポイントは、社内の業務実態に即した内容のルールを決めることです。
また、ルールは一度作って終わりにするのではなく、技術の進化や業務内容の変化に応じて定期的に見直し、随時アップデートしていきましょう。
ユーザーの認証方法を工夫する
認証の強化は、不正アクセスやなりすましによる情報漏洩を防ぐ上で非常に効果的です。
従来のIDとパスワードのみの認証ではリスクが高いため、近年では多要素認証の導入が進んでいます。
これは、パスワードに加えてワンタイムパスコードや生体認証など、複数の要素を組み合わせて本人確認を行う方法です。
また、パスワードの定期的な変更ルールや、辞書攻撃を防ぐための複雑な文字列ルールの導入も有効です。
権限付与を適切に行う
業務上必要な情報のみにアクセスできるようにする「最小権限の原則」は、情報漏洩を防ぐための基本的な考え方といえます。
全ての従業員に広範囲あるいは無制限のアクセス権を与えてしまうと、意図せぬ誤操作や内部不正の温床になりかねません。
部署や役職、業務内容に応じて権限を細かく設定し、誰がどの情報にアクセスできるかをしっかりと管理することで、情報漏洩を防ぎやすくなります。
また、異動や退職時には権限の見直しや解除を速やかに行うことが大切です。
加えて、アクセスログの記録と定期的な監査も、不正利用の抑止力となります。
データの暗号化を行う
暗号化は、デバイスの盗難や紛失、通信傍受といったリスクに備える基本対策です。
情報が外部に流出してしまった場合でも、データが暗号化されていれば内容の漏洩を防げる可能性があります。
このときのポイントは、ファイルフォルダ単位ではなく、
・メール送信時の暗号化
・社内クラウドやストレージサービス保存時の暗号化
といったように、複数レイヤーで対策をしておくことです。
特に機密性の高い情報については、暗号鍵の管理や複合ポリシーの設定まで丁寧に行い、利便性とセキュリティの両立を図りましょう。
情報セキュリティ教育を行う
メールの誤送信やフィッシングメール(サイト)の閲覧、USBメモリの無断使用など、人為的ミスは情報漏洩の主因です。
だからこそ、従業員の情報セキュリティ教育を徹底して行う必要があるのです。
年1回の研修や、最新の教育情報に基づいた定期的な注意喚起などを行うことで、企業全体としてのセキュリティ意識を高められます。
情報セキュリティ教育については、こちらの記事で詳しく解説していますので、気に
なる⽅はぜひチェックしてみてください。
まとめ
情報漏洩は、企業の存続にかかわる深刻なリスクをはらんでいます。
たとえ一度の事故でも、顧客や取引先の信頼を失い、事業継続が困難になる場合もあります。
このような事態を避けるためには、技術的なセキュリティ対策だけでなく、社内の情報管理体制や従業員教育までを含めた総合的な対策を行うことが大切です。
近年では、サイバー攻撃の手法も巧妙化しており、常に最新のリスクを把握しながら対策を見直していく姿勢が求められます。
サイバー攻撃は、規模や業種に関係なく、全ての企業にとってリスクとなりますので、今回紹介したことを参考にしながら、今できる対策を着実に実行していきましょう。