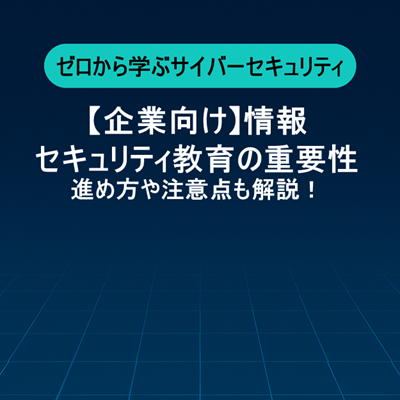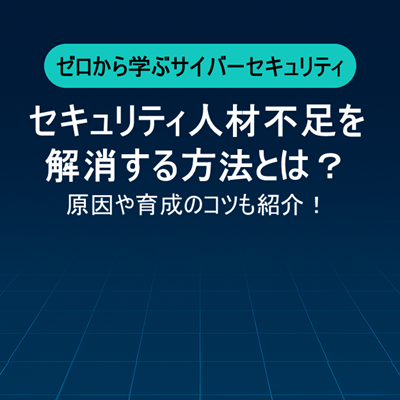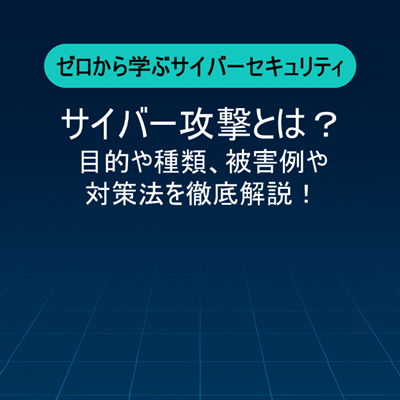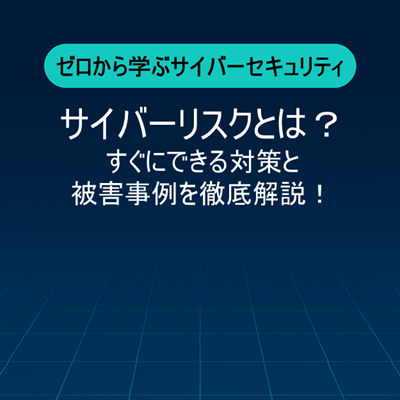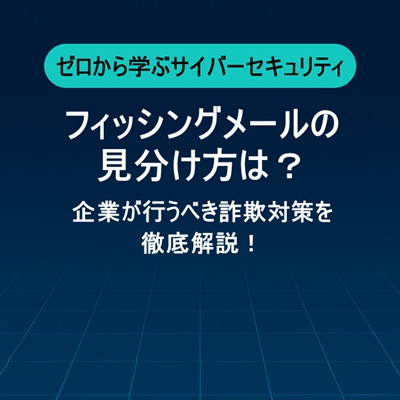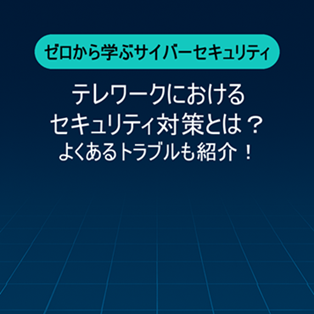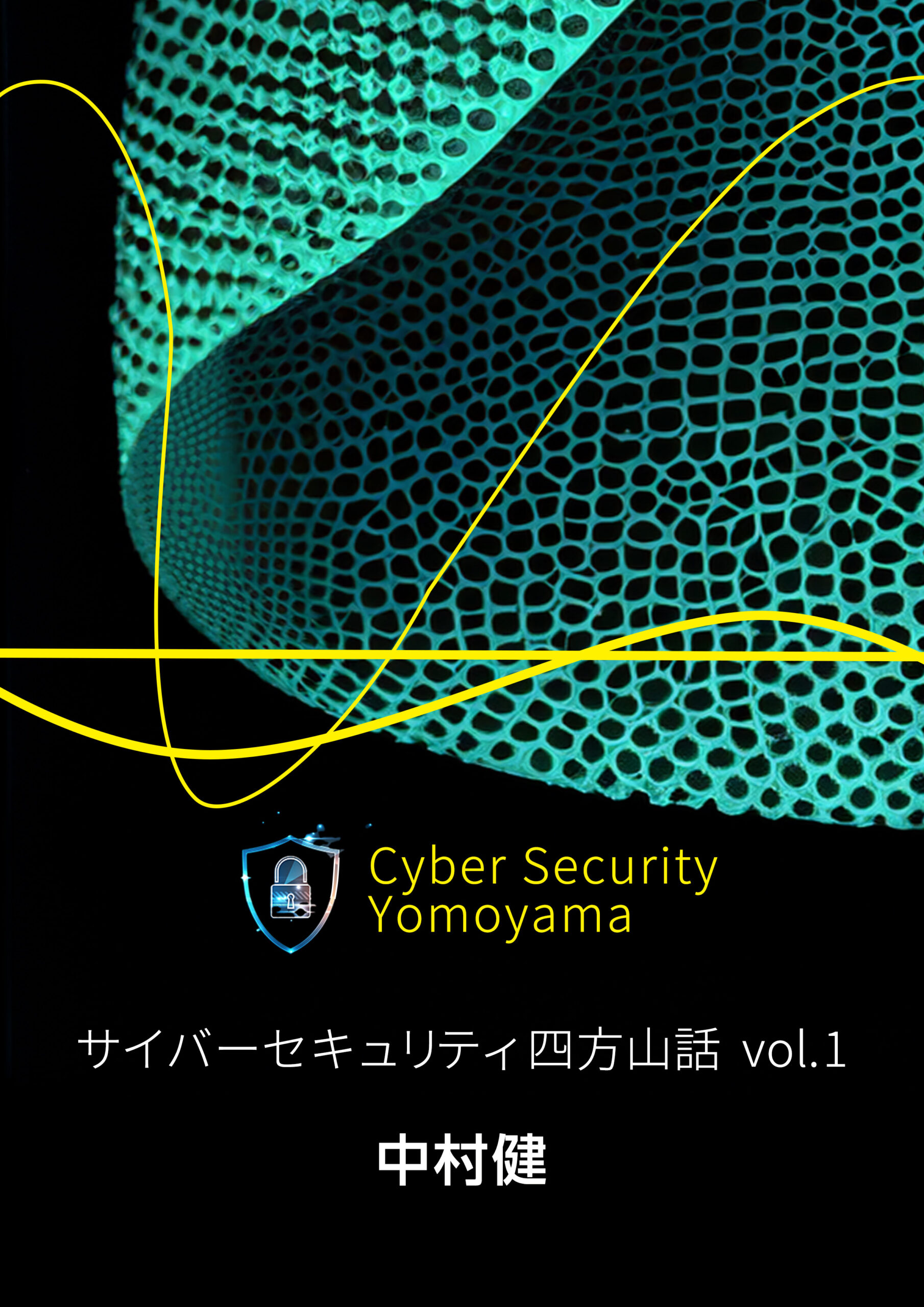企業のSNSに潜む情報漏洩のリスク|原因や対策を徹底解説!
利用者が多く、それでいて拡散性の高いSNSは、プライベートだけでなくビジネスにも活用され始めています。
自社の認知拡大やファン獲得、それから新規サービスのPRなど、さまざまな目的で活用できるSNSは、今後も企業にとって欠かせないマーケティングツールとして活躍していくでしょう。
そんな利便性の高いSNSですが、使い方を誤ると重大なトラブルに繋がります。
中でも代表的なのが「情報漏洩」です。
そこで今回は、SNSに潜む情報漏洩のリスクについて詳しく解説していきます。
SNSをビジネスに活用する企業が増えている
現代のビジネスシーンにおいて、SNSは欠かせないマーケティングツールとなっています。
・X(旧Twitter)
・Instagram
・Facebook
・TikTok
といった各種SNSを通じて企業が情報発信を行うことで、低コストかつスピーディに自社の商品やサービスを広められます。
特に中小企業やスタートアップにとって、広告予算を抑えながら多くのユーザーにリーチできるSNSは非常に魅力的です。
その他、採用活動やブランディング、顧客とのエンゲージメント強化など、さまざまな効果に期待できます。
特に近年では、企業の「中の人」が顔を出して発信するケースも多くなり、企業の透明性や親しみやすさを演出する手段としても機能しています。
SNSと情報漏洩
ビジネスとの相性が良く、何かと便利なSNSですが、情報漏洩のリスクは無視できません。
担当者がうっかり機密情報や顧客データ、内部事情などを投稿してしまったり、企業アカウントで個人的な投稿をしてしまったりするケースも多く発生しています。
また、従業員個人のSNS投稿から、業務内容や取引先情報が漏れてしまうリスクもあります。
SNSはリアルタイム性が高く、拡散力が強いため、ひとたび不適切な情報が公開されれば、瞬く間に拡散し、企業の信用に大きなダメージを与えてしまいます。
SNSを通じた情報漏洩は、企業規模にかかわらず起こり得る重大なリスクであるため、セキュリティを高めるための工夫や取り組みも行わなければなりません。
企業SNSの情報漏洩事例
SNSは拡散性が高く、良い情報も悪い情報もあっという間に拡散されてしまいます。
ここでは、SNSを通じた企業の情報漏洩事例をいくつか紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
未公開製品の情報漏洩
企業SNSでは、新製品の開発状況やコンセプトが話題性のある投稿として扱われることが多いですが、投稿内容によっては未発表の情報が外部に漏れてしまうことがあります。
製品の写真に設計資料が写り込んでいたり、開発チームのコメントから発売時期や仕様が特定されたりといったケースは少なくありません。
このような情報漏洩は、競合他社に情報が渡るだけでなく、株価への影響やブランドイメージの低下にも繋がります。
特に上場企業においては、インサイダー情報とみなされる恐れもあるため注意してください。
業績情報の漏洩
業績に関する情報も、SNS上でうっかり漏洩しやすい内容の1つです。
特に気をつけなければならないのが、未公開あるいは非公開の業績情報が出回ってしまうケースです。
業績情報の漏洩は、取引先などの関係者にも情報管理の観点で不信感を与えてしまう重要なインシデントとなります。
場合によっては、それが原因で契約を切られたり、トラブルに発展したりするケースもあるため投稿内容には十分注意しなければなりません。
アカウントを乗っ取られる
SNSのアカウント乗っ取りは、情報漏洩だけでなく、企業ブランドへの深刻なダメージをもたらします。
乗っ取られたアカウントから不適切な投稿が行われれば、顧客の信頼を失うだけでなく、謝罪や事態収拾のために多大なリソースが必要になります。
その他、DMなどでやり取りしていた顧客の個人情報や問い合わせ内容が流出するケースもあり、そうなると顧客離れは避けられません。
このようなトラブルを防ぐためには、二段階認証やパスワードの複雑化、アクセス権限の管理など、基本的な対策を徹底するとともに、社内のセキュリティ教育も強化していくことが大切です。
顧客情報の漏洩
SNSは、顧客との交流や問い合わせ対応などにも使える利便性の高いツールです。
しかし、個人情報の管理を誤ると重大なインシデントに繋がります。
実際に、
・DMで受け取った個人情報をスクショ付きで投稿した
・顧客氏名やメールアドレスが記載された画面を公開してしまった
という事例が後を絶ちません。
そうなれば、顧客離れはもちろん、企業イメージの低下に繋がりやすくなります。
場合によっては、情報漏洩が原因で倒産に追い込まれてしまうケースもあるため注意が必要です。
取引先企業の情報漏洩
取引先との未発表プロジェクトや、契約内容などを公開してしまう事例も後を絶ちません。
具体的には、共同開発中の製品名や企業ロゴが写った資料を公開してしまったり、打ち合わせ中の様子をアップしてしまったりといったケースです。
このようなトラブルが起こると、取引先の信頼を損ない、場合によっては損害賠償を請求されることもあります。
SNSで情報漏洩が起こる原因
SNSで情報漏洩が起こる原因は、主に以下3つです。
・SNSリスクの理解不足
・SNS運用マニュアルの整備不足
・SNSアカウントの管理不足
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
SNSリスクの理解不足
多くの企業では、SNSをマーケティングや採用に活用していますが、SNSのリスクを十分に理解していない企業も多いです。
この状態で運用を続けると、ちょっとしたミスや認識の違いから情報漏洩に繋がってしまうことがあります。
このようなトラブルを防ぐためには、企業がSNSの危険性や過去のトラブルを共有し、リスク意識を全ての従業員に浸透させることが大切です。
SNS運用マニュアルの整備不足
企業によっては、SNSのアカウント運用ルールが曖昧で、
・誰がどのように運用するか
・どのような情報を扱うべきなのか
などが明確になっていない場合もあります。
その結果、担当者が判断に迷い、不適切な内容を投稿してしまうのです。
SNS運用マニュアルを整備しておくことで、投稿内容や投稿の雰囲気などを統一できるため、情報漏洩をはじめとするさまざまなリスクを回避しつつ、効率的に運用が行えるようになります。
SNSアカウントの管理不足
SNSアカウントのパスワード管理やアクセス権限が適切に行われていないと、アカウントの乗っ取りや不正アクセスに繋がります。
特に、複数人でアカウントを共有している場合、パスワードの使い回しやメモでの管理といった危険な運用が行われがちです。
また、退職者がアカウントにアクセスできる状態になっていれば、不正投稿や情報漏洩といったリスクが高まります。
SNSは企業の顔となる存在であるため、アカウント管理は厳格に行いましょう。
SNSの情報漏洩が企業に与える影響
企業が運営するSNSで情報漏洩が起こると、以下のようなトラブルに繋がります。
・イメージの低下
・風評被害の蔓延
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
イメージの低下
SNSで情報漏洩が発生すると、企業のブランドイメージは大きく損なわれます。
特に未公開情報や機密情報が流出した場合、企業の情報管理体制に関する疑念が世間に広がります。
そうなれば、売上の低下や取引先数の減少は避けられないでしょう。
先ほども解説したように、SNSは拡散力が強いため、ちょっとした投稿でも一気にイメージが低下する可能性があります。
一度失った信用や信頼を取り戻すにはかなりの時間がかかりますので、SNSアカウントは慎重に運用していきましょう。
風評被害の蔓延
SNS上の情報には、事実だけでなく誤解や憶測も混ざっています。
情報漏洩をきっかけに、自社とは全く無関係のデマや悪評が広がってしまえば、風評被害を受ける可能性が高くなります。
例えば、
「この会社は顧客の情報を悪用しているらしい」
という情報が拡散されれば、採用や営業などあらゆる面で悪影響が出てしまうでしょう。
たとえ事実無根の情報であっても、一度広まった悪評は消し去るのが困難であり、企業活動全体に深刻な打撃を与えるため注意が必要です。
SNSの情報漏洩対策4選!
情報漏洩をはじめとするさまざまなリスクが潜むSNSを上手に活用していくためには、徹底的なリスク対策が必要不可欠です。
以下4つの施策を導入することで、被害の予防に繋げやすくなります。
・リスク研修を実施する
・SNS運用のガイドラインを制定する
・秘密保持契約を締結する
・SNS運用チームを作る
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
リスク研修を実施する
従業員に対する情報セキュリティ教育は、SNSを活用している企業にとって最も基本的かつ重要な対策です。
SNSの基本や、SNSに潜むリスクなどを徹底的に指導することで、担当者を含む従業員全員の意識を高められます。
また、座学だけでなく、過去の情報漏洩事例を用いたケーススタディや、模擬炎上対応などのリスク研修を実施することで、実践的なリスク対応力が身につきます。
SNS運用のガイドラインを制定する
SNSの投稿基準や禁止事項、担当者の役割分担などを文書化した「ガイドライン」は、運用ミスによる情報漏洩を防ぐ強力なツールです。
例えば、
「未発表の製品や取引先情報には触れない」
「投稿は必ずダブルチェックを経て公開する」
といったルールを明文化しておくことで、迷いや判断ミスを防げます。
秘密保持契約を締結する
業務委託先や外部パートナーにSNS運用を委託する場合は、情報の取り扱いに関する秘密保持契約を必ず締結しましょう。
そうすることで、運用中に得た機密情報を無断に持ち出されたり、公開されたりといったリスクを軽減できます。
また、秘密保持契約は心理的な抑止効果にも期待できるため、悪意のある情報漏洩も予防しやすくなります。
SNS運用チームを作る
SNS運用を個人任せにせず、複数人によるチーム体制で行うことも、情報漏洩対策としてはかなり効果的です。
1人だけで投稿や管理を行うと、誤投稿の発見が遅れたり、セキュリティチェックが甘くなったりしがちですが、運用チームを組織化すれば、投稿内容のレビュー体制や緊急時のフロー整備なども行えます。
その結果、リスクの最小化に繋げやすくなるのです。
まとめ
SNSは、企業活動に大きなメリットをもたらす一方で、情報漏洩のリスクと常に隣り合わせです。
しかし、適切な教育やルール、体制を整えることで、情報漏洩をはじめとするさまざまなリスクを大幅に軽減できます
ガイドラインの整備や研修の実施、秘密保持契約の締結など、できるところから段階的に取り組んでいきましょう。
安全なSNS運用体制を構築することが、企業の信頼とブランド価値を守る第一歩となります。