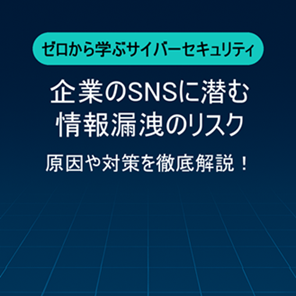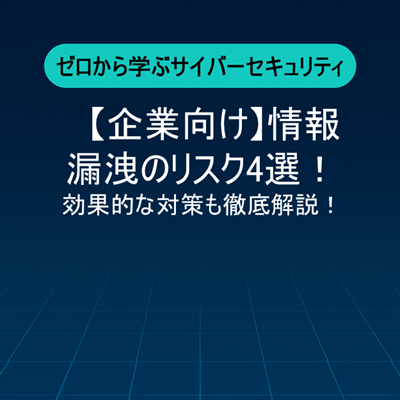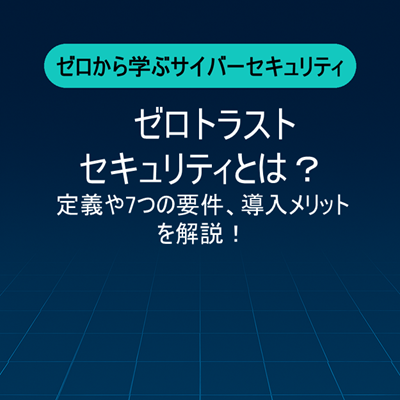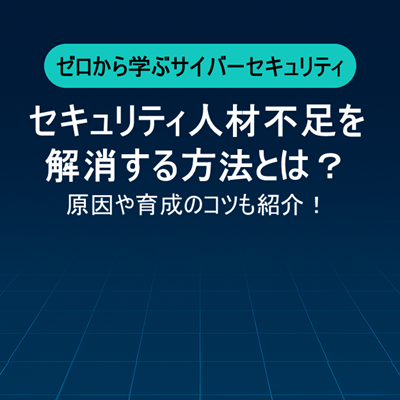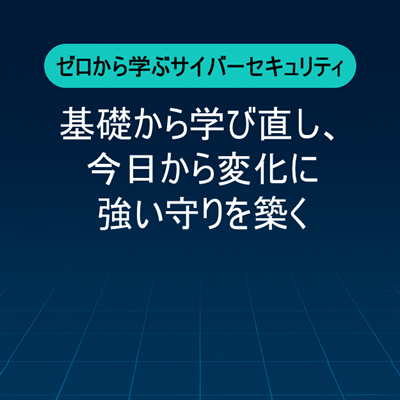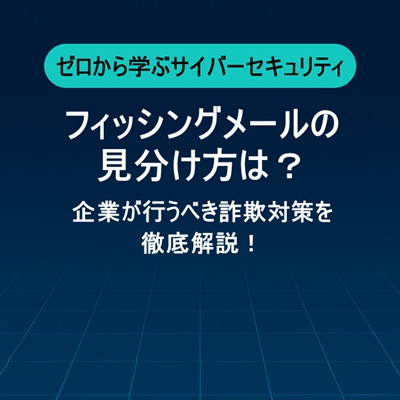【企業向け】情報セキュリティ教育の重要性|進め方や注意点も解説!
サイバー攻撃は、もはや一部の大企業だけの問題ではありません。
中小企業や医療機関、教育機関など、あらゆる業種や規模の組織が標的となり得る時代に突入しています。
特に昨今では、システムの脆弱性だけでなく、従業員のケアレスミスや知識不足を突いた攻撃が増加傾向にあります。
こうした人為的リスクを最小限に抑えるためには、従業員に向けた情報セキュリティ教育が欠かせません。
そこで今回は、情報セキュリティ教育の重要性や進め方、注意点について詳しく解説していきます。
情報セキュリティ教育とは?
情報セキュリティ教育とは、従業員一人ひとりが業務で扱うデータやシステムを安全に運用できるよう、必要な知識やスキル、意識を身につけさせる取り組みのことです。
近年では、フィッシング詐欺やマルウェア感染による情報漏洩が増加しており、中でも不審なメールの添付ファイルをクリックしたことがきっかけでセキュリティ事故が起こるケースが増えています。
情報セキュリティ教育を徹底することで、従業員一人ひとりに正しい知識を共有できるため、思わぬ事故やトラブルを防ぎやすくなるのです。
情報セキュリティ教育を行うべき理由
サイバー攻撃の約7割は、ヒューマンエラーによるものだといわれています。
先ほども解説したように、不審なメールに添付されたリンクをクリックしたり、テレワーク先で無防備なWi-Fiに接続したり、パスワードを再利用したりといったミスが、セキュリティ事故のきっかけになってしまうのです。
これらのミスは、高度な防御システムさえも無力化してしまいます。
つまり、企業がどれだけセキュリティ対策に力を入れていたとしても、従業員が正しい知識を身につけていなければほとんど意味がないということです。
実際に、従業員のヒューマンエラーが原因で、機密情報が漏洩したり、金銭的損失を被ったりするケースも増えています。
このようなトラブルを防ぐためには、定期的に情報セキュリティ教育を行い、従業員のセキュリティリテラシーを底上げする必要があります。
情報セキュリティ教育の進め方
情報セキュリティ教育は、以下のステップに沿って進めるのがおすすめです。
ステップ1:目的と学習テーマを明確にする
ステップ2:対象者を絞り込む
ステップ3:実施時期と頻度を決める
ステップ4:実施方法を決める
ステップ5:効果測定を行う
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
ステップ1:目的と学習テーマを明確にする
情報セキュリティ教育を効果的に進めるには、まず「何のために実施するのか」を明確にしなければなりません。
「個人情報漏洩の対策」「テレワーク環境下でのセキュリティ意識向上」など、目的によって必要な学習テーマが変わります。
目的が曖昧なままでは、内容が浅くなってしまい、従業員の意識改革や行動変容に繋がりません。
そうなれば、情報セキュリティ教育を行う意味が無くなってしまうため、まずは目的を明確にするところから始めていきましょう。
ステップ2:対象者を絞り込む
サイバー攻撃による被害を防ぐためには、全従業員に情報セキュリティ教育を実施することが大切です。
しかし、必ずしも全ての従業員に対して、一斉に情報セキュリティ教育を行う必要はありません。
むしろ、対象者を絞り、その対象者に合った内容で教育を実施することで、浸透度や理解度が高まります。
例えば、
管理職:リスク管理やインシデント対応の指揮に関する教育
システム管理者:脆弱性対策やアクセス制御の技術的知識の指導
一般社員:日常業務に潜むリスクへの対応法指導
など、役職や立場に合わせて内容を調整することで、より高い効果に期待できます。
ステップ3:実施時期と頻度を決める
情報セキュリティ教育は、一回限りで終わらせるのではなく、定期的に行うことが大切です。
なぜなら、サイバー攻撃の手口や法制度は日々進化しているからです。
従業員のセキュリティ意識を常にアップデートしていくためにも、年に1回以上は教育機会を設けるようにしましょう。
また、実施時期については新入社員が入社してきたときや、新たな制度を導入したときなど、節目ごとに行うのがおすすめです。
ステップ4:実施方法を決める
情報セキュリティ教育の実施方法には、以下のような種類があります。
・集合研修
・eラーニング
・動画教材
・シミュレーション型訓練
それぞれで特徴が大きく異なるため、対象者の勤務形態や目的などに合わせて選びましょう。
例えば、全国に支社がある企業ではeラーニングが効果的です。
また、テレワーク主体の組織ではオンライン研修や動画配信が実用的といえるでしょう。
重要なのは、受講者が「自分ごと」として捉えられるようなリアリティのある内容にすることです。
自社に合った方法がわからないという場合は、それぞれの方法を試験的に導入し、その中で最も効果が高かった方法を採用しましょう。
ステップ5:効果測定を行う
情報セキュリティ教育の実施フローにおいて最も重要なのが、効果測定です。
内容の理解度や行動変容の状況などを可視化し、次回の教育機会に活かすことで、より効率的に正しい知識を浸透させられるようになります。
PDCAを回すにはやや手間がかかりますし、場合によっては多少のコストがかかってしまうかもしれませんが、従業員の理解度を確認し、内容を最適化させていくためには欠かせない作業ですので、必ず実施してください。
情報セキュリティ教育のコンテンツ例
情報セキュリティ教育と聞いて、どのようなコンテンツを用意すればいいかわからないと悩んでしまっている担当者もたくさんいるでしょう。
そんなときは、以下のようなコンテンツを作成してみてください。
・個人情報保護の基礎
・情報セキュリティの運用ルール
・攻撃メールの基礎
・公衆無線LANの危険性
個人情報保護の基礎
個人情報の取り扱いは、法令遵守だけでなく、企業の信用維持にも直結する重要なテーマです。
そのため、個人情報の定義(氏名・住所・電話番号など)や、漏洩時の法的責任、取り扱い時の注意点(保存方法、アクセス制限、送信ミスの防止)などを網羅的に伝えることが大切です。
このときに、実際の個人情報漏洩事例を紹介することで、リスクの深さを実感させやすくなります。
情報セキュリティの運用ルール
社内のセキュリティルールは、従業員の行動を標準化し、リスクを未然に防ぐための重要な指針です。
そのため、
・社内ネットワークへのアクセス制限
・USBメモリなどの外部デバイスの取り扱い
・業務端末の持ち出しルール
・ソフトウェアのアップデート義務
などを中心に説明しましょう。
ルールの背景にある目的やリスクを明確に伝えることで、従業員の納得感を高めると同時に、ルール違反の抑制にも繋げやすくなります。
攻撃メールの基礎
サイバー攻撃を行うハッカーやクラッカーは、従業員の知識不足やケアレスミスを狙ってくることが多いです。
そのため、
・不審なメールの見分け方
・偽リンクの特徴
・添付ファイルの安全確認方法
といった、基本的な内容を具体的に解説しましょう。
過去に出回った攻撃メールの例を提示し「どこが怪しいか」をディスカッションするワーク形式を取り入れると、より実践的な学びになります。
公衆無線LANの危険性
リモートワークやテレワークが一般化している昨今では、カフェやレストランなど、オフィス以外で仕事をする従業員が増えています。
このときに役立つのが、公衆無線LANです。
表示されているパスワードを入力するだけでWi-Fiを使えるようになるため、素早くインターネットにアクセスできます。
一方で、通信の暗号化が不十分なケースも多く、情報漏洩のリスクも比較的高いです。
そのため、
・暗号化が不十分なWi-Fiを使用した場合のリスク
・安全なVPNの利用方法
・業務データの送受信を避けるべきシーン
などをしっかりと伝えましょう。
情報セキュリティ教育を行うときの注意点
従業員に情報セキュリティ教育を実施するときの注意点は、以下の通りです。
・セキュリティポリシーを明確にする
・対象者をできるだけ細かく絞る
・適切な学習方法を選定する
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
セキュリティポリシーを明確にする
情報セキュリティ教育を効果的に実施するには、組織全体で共有すべき「セキュリティポリシー」を明確にしておくことが大切です。
これは、従業員が守るべき情報管理の基本方針やルールを体系的に示したものであり、指針が曖昧なままだと教育効果が薄れます。
とはいえ、ポリシーが現場の実情に合っていなければ、従業員の行動に落とし込むことが難しくなりますので、まずは現場の状況や課題などを洗い出すところから始めましょう。
対象者をできるだけ細かく絞る
情報セキュリティに関するリスクや対処法は、部門や職種ごとに大きく異なります。
そのため、対象者を一律に扱うのではなく、役職や担当業務に応じた細やかなグループ分けを行いましょう。
営業部門:モバイルデバイスの扱い方
管理部門:機密情報の扱い方
IT部門:システムの脆弱性に関する知識
このように、適切なターゲティングを行い、各部門に応じた教育をほどすことで、理解度や定着率を高めやすくなります。
適切な学習方法を選定する
先ほども解説したように、情報セキュリティ教育の進め方にはいくつかの種類があります。
それぞれにメリットやデメリットがあり、業種や対象者、目的などによって最適な方法が変わってくるため、自社に合った方法を探していきましょう。
また、学習の進め方については、一方的に教えるのではなく、従業員が主体的に学べる「参加型のスタイル」を採用するのがおすすめです。
そうすることで、従業員に「自分ごと」として捉えてもらえるようになるため、理解度や定着率の向上、継続的な学習機会の提供などにも繋げやすくなります。
まとめ
情報セキュリティ教育は、組織全体のセキュリティレベルを底上げするための重要な施策です。
サイバー攻撃の手口や情報セキュリティに関する知識は日々アップデートされていきますので、企業としてのリスクを軽減するためにも、業務効率を最大化するためにも、定期的に教育機会を設けましょう。
そうすることで、サイバー攻撃に強い企業体質を構築できるようになります。